2025年7月3日、岩手大学にて「AFSeC×COI-NEXT 畜産ミートアップ!第5回セミナー」が開催されました。
本セミナーは、畜産業の持続可能性と地域循環の実現を目指し、「飼料から食卓までのフードバリューチェーンを考える」をテーマに、現場の実践者と研究者が一堂に会し、知見と課題を共有するこのイベント、どんな内容だったのか、現役畜産農家の私が参加者目線でレポートします。
イベントプログラム
挨拶
岩手大学農学部 澤井教授(岩手大学COI-NEXT プロジェクトリーダー)
講演
1.コントラクター事業の課題と今後の展望
講師:盛岡大学文学部社会文化学科准教授 高畑 裕樹 氏
2.日本短角種における2シーズン放牧を取り入れた低コスト肥育技術の取り組み
講師:岩手県農業研究センター 畜産研究所主席専門研究員兼外山研究室長 山口 直己 氏
3.資源循環型畜産に貢献する牧草生産、温暖化に対応した東北地域向けの牧草新品種と省力的な草地管理技術
講師:農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター
緩傾斜畑作研究領域生産力増強グループ 上席研究員 東山 雅一 氏
4.Ark館ヶ森における耕畜連携による資源循環と消費者と繋がる六次産業化の取り組み
株式会社アーク総務部 佐々木 信広 氏
総合討論 「飼料から食卓までのフードバリューチェーンを考える」
閉会挨拶
イベントレポート
開会挨拶
岩手大学農学部 澤井教授(岩手大学COI-NEXT プロジェクトリーダー)
セミナーの冒頭では、岩手大学の澤井先生より開会の挨拶がありました。
先生は、畜産業が直面する多様な課題に対して、研究者・実践者・消費者が一体となって考える場の重要性を強調。今回のセミナーが「飼料生産」「畜産経営」「消費者との接続」という3つのボリュームで構成されていることを紹介し、Vol.1では「飼料生産」に焦点を当てて議論を深めることが目的であると述べられました。


講演
1.コントラクター事業の課題と今後の展望
講師:高畑 裕樹 氏(盛岡大学文学部社会文化学科 准教授)
高畑氏は、岩手県H地域の酪農地帯を事例に、コントラクター(農作業受託組織)の現状と課題を報告。酪農家の高齢化と後継者不足が進む中、飼料生産の外部化が進まず、若手農家に作業が集中する構造的な問題が浮き彫りになっています。
特に、地域内での労働力調整に依存している現状では、体力のある若手が高齢農家の作業を請け負う形になっており、本来規模拡大に向かうべき農家が作業負担に追われているという課題が指摘されました。
北海道のTMRセンターのような外部化モデルとの比較を通じて、岩手県における広域的な飼料流通・生産体制の必要性が提言されました。また、飼料生産に対する農家の「自家配合へのこだわり」が品質のばらつきや連携の障壁になっている点も課題として挙げられました。
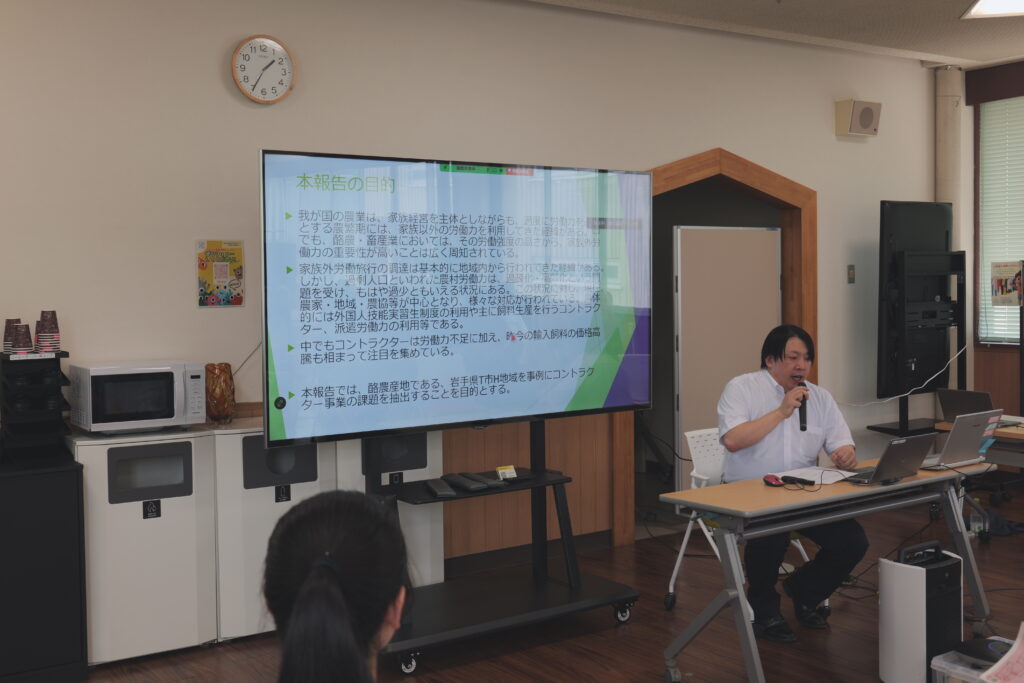

2.日本短角種における2シーズン放牧を取り入れた低コスト肥育技術の取り組み
講師:山口 直己 氏(岩手県農業研究センター 畜産研究所 主席専門研究員 兼 外山研究室長)
山口氏は、岩手県の草地資源を活かした「2シーズン放牧」の試験研究について報告。繁殖期と肥育期の2回に分けて放牧を行うことで、飼料コストの削減とアニマルウェルフェアの向上を目指す取り組みです。
放牧後の体重増加の停滞や草の質・量の確保といった課題も共有され、補助飼料の給与タイミングや放牧馴致の工夫が必要であるとされました。特に、放牧開始時の草の成長状況や牛の順応性が成長に大きく影響することが明らかになりました。
また、農業大学校や大学生の実習受け入れによる若手人材育成の可能性にも言及され、放牧監視をアドベンチャー体験として捉える若者の感性に着目した教育的アプローチが紹介されました。
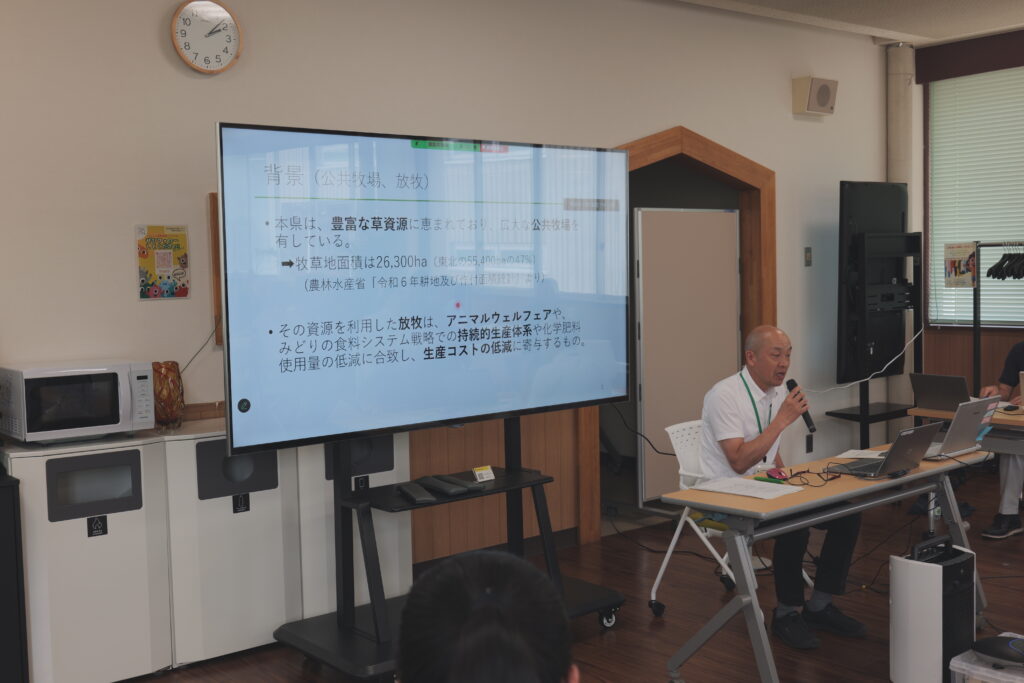

3.資源循環型畜産に貢献する牧草生産、温暖化に対応した東北地域向けの牧草新品種と省力的な草地管理技術
講師:東山 雅一 氏(農研機構 東北農業研究センター 緩傾斜畑作研究領域 生産力増強グループ 上席研究員)
東山氏は、資源循環型畜産の現状と課題をデータに基づいて解説。日本の畜産が濃厚飼料の輸入に依存しており、資源循環が成立していない現状を指摘しました。特に、鶏・豚はほぼ100%輸入飼料依存であり、持続可能性の観点から大きな課題となっています。
また、気候変動に対応するための新たな牧草品種(クワトロTK5、夏越しペレニアルライグラスなど)や、雑草抑制のための草地管理技術(除草剤2回処理法、簡易更新法)についても紹介。異業種からのコントラクター参入の可能性や、地域資源を活かした持続可能な畜産モデルの構築に向けた提言がなされました。


4.Ark館ヶ森における耕畜連携による資源循環と消費者と繋がる六次産業化の取り組み
講師:佐々木 信広 氏(株式会社アーク 総務部)
佐々木氏は、株式会社アークが実践する資源循環型農業と6次産業化の取り組みを紹介。養豚から排出される糞尿を有機肥料として活用し、地域農家と連携して飼料米を生産・飼料化するという、15年以上続く循環の仕組みを説明しました。
また、自社生産品を使った加工・販売を行うファームマーケットやレストランの運営を通じて、消費者との接点を重視した6次産業化の実践例が共有されました。来場者数は年間最大10万人に達し、関東・関西の高品質スーパーへの販路拡大も進めているとのことです。
さらに、消費者が生産現場を体験し、食と農のつながりを実感できる場づくりを重視しており、家族連れをターゲットにした体験型農業の展開が紹介されました。


総合討論:飼料から食卓までのフードバリューチェーンを考える
モデレーターの澤井先生の進行のもと、登壇者全員による総合討論が行われました。コントラクターの外部化、若手人材育成、飼料米の供給課題、大規模化と小規模化の両立、消費者との接点など、多岐にわたるテーマで活発な議論が展開されました。
特に、若者の新規参入支援や、地域資源を活かした畜産モデルの構築に向けた議論が深まり、今後のCOI-NEXTの方向性にもつながる内容となりました。


◆コントラクターの役割と課題
高畑氏
- 小規模地域では労働力の外部化が進まず、若手農家に作業が集中する傾向。
- 北海道のTMRセンターのような外部化モデルを岩手でも目指すべき。
- 餌作りへのプライドが障壁になるが、若手農家は合理性を重視する傾向がある。
東山氏
- コントラクターは技術的には十分可能。マニュアル化すれば異業種参入も現実的。
- 異業種(例:建設業)からの参入には市場の整備が必要。価格設定が重要。
- 粗飼料市場が未整備であることが参入障壁になっている。
◆放牧と若手人材育成
山口氏
- 農業大学校や日大の学生が放牧監視実習に参加。特に日大生は新鮮な体験として好評。
- アドベンチャー感覚で放牧監視を楽しむ姿が見られ、若者の関心を引く可能性あり。
- 今後は宿泊型の実習や動画記録によるエビデンス収集も検討。
◆資源循環と飼料米の課題
佐々木氏
- 有機肥料の生産と活用を通じて地域循環を実現。完熟肥料の品質管理を徹底。
- 飼料米の生産は食用米価格の高騰により減少傾向。今後は遊休農地の活用や地域連携が鍵。
- 牛乳・乳製品は地域の生産者から調達。将来的には自社で牛の飼養も検討。
◆大規模化 vs 小規模化と持続可能性
各講師の見解
- 大規模化は経営安定に寄与するが、過剰投資によるリスクもある。
- 小規模でも高付加価値化によって持続可能な経営は可能。
- 畜産経営は「相反するものではなく、別の選択肢」として捉えるべき。
◆若者参入と持続性の両立
- 若者の新規参入には初期投資の負担が大きく、支援体制(TMRセンター、研修制度など)が必要。
- 小規模でも高単価で販売できる仕組みがあれば持続可能性は確保できる。
- 消費者との接点を持ち、食と農のつながりを体験できる場づくりが重要。
閉会挨拶
岩手大学農学部 平田准教授(AFSeC副センター長)
セミナーの締めくくりとして、平田先生より閉会のご挨拶がありました。
平田先生は、今回のセミナーが「飼料から食卓までのフードバリューチェーンを考える」シリーズの第1回として開催されたことを振り返り、各講演が生産現場の課題や未来へのヒントに富んだ内容であったことを評価されました。
また、総合討論では「大変エキサイティングで示唆に富む議論が展開された」と述べ、今後への期待を込めて、参加者に継続的な関心と参加を呼びかけました。
「本日の学びや気づきが、今後の実践あるいは連携の第一歩となることを願っています」との言葉で締めくくられ、講演者・参加者への感謝が述べられました。

まとめ
本セミナーは、畜産業の現場から消費者までをつなぐフードバリューチェーンの全体像を描き出す貴重な機会となりました。
資源循環、若手育成、地域連携、気候変動対応など、多様な視点が交差する中で、持続可能な畜産の未来に向けた実践と議論が深まりました。
今後のVol.2では、肉質や消費者との接点など、より下流のテーマが扱われる予定です。畜産の未来を共に考える場として、引き続き多くの方々の参加が期待されます。

