2025年7月15日、岩手大学COI-NEXT拠点にて「畜産ミートアップ!第6回セミナー」が開催されました。
本セミナーは、畜産が持つ非市場的価値を地域社会の持続可能性と結びつけることを目的に、専門家による講演と活発な総合討論が行われました。どんな内容だったのか、現役畜産農家の私が参加者目線でレポートします。
イベントプログラム
開会挨拶
岩手大学COI-NEXT拠点運営機構設置責任者 水野 氏
講演1
「畜産の多面的機能を『地域価値』に結びつける!」
講師:前田 浩史 氏(前・一般社団法人Jミルク専務理事)
講演2
「酪農による都市と農村の結びつきについて —日本の酪農乳業の都市史—」
講師:金谷 匡高 氏(法政大学エコ地域デザイン研究センター 客員研究員)
講演3
「農業遺産『重要文化財小岩井農場施設』」
講師:辰巳 俊之 氏(公益財団法人小岩井農場財団代表理事 兼 小岩井農牧株式会社代表取締役社長)
総合討論:畜産の多面的機能を見える化する
イベントレポート
開会挨拶
セミナーの冒頭では、岩手大学COI-NEXT拠点運営機構設置責任者である水野氏より開会の挨拶がありました。
水野氏は、「畜産の多面的機能には、生物多様性の保護、景観の保全、文化の継承などが含まれます。本セミナーでは、近代畜産の遺産や景観、文化といった地域支援に焦点を当て、地域価値としての畜産を考える機会としたい」と述べられました。
この挨拶は、畜産を単なる生産活動としてではなく、地域の文化・環境・社会と深く結びついた存在として捉える視点を提示するものであり、セミナーの方向性を明確に示すものでした。


講演1:畜産の多面的機能を『地域価値』に結びつける!
講師:前田 浩史 氏(前・一般社団法人Jミルク専務理事)
前田氏は、畜産の非市場的価値(生物多様性、景観、文化、地域経済など)を「地域共通価値」として再定義する必要性を強調されました。
講演では、農業人口の減少や高齢化が進む中で、畜産が地域の持続可能性にどう貢献できるかを問い直す必要があるとし、歴史的な視点から「牛のいる暮らし」が地域文化の核であることを強調されました。
また、SDGsの視点から、経済・社会・環境の調和を目指す農業のあり方を提案され、岩手県北部の畜産モデルを「持続可能な地域社会の実験」として位置づけるべきであると述べられました。
さらに、地域の若者が地元に残る理由として「豊かさ」や「愛着」が重要であるとし、これらを育むためには畜産の多面的機能を見える化し、地域の誇りとして再認識する必要があると語られました。



講演2:酪農による都市と農村の結びつきについて —日本の酪農乳業の都市史—
講師:金谷 匡高 氏(法政大学エコ地域デザイン研究センター 客員研究員)
金谷氏は、建築学と都市史の視点から、日本の酪農が都市と農村の関係性にどのような影響を与えてきたかを丁寧に解説されました。
明治期の東京では、旧武士階級が失業後に自邸の敷地を活用して酪農を始める「士族授産」の動きが見られました。特に、商業が禁じられていた「武家地」が、広大な敷地を活かして牧場として再利用され、都市の中心部に多数の搾乳所が存在していたことが地図や広告資料から明らかになっています。
また、都市化の進行により繁殖地は郊外へと移り、搾乳牛のみが都市部に運ばれるようになります。新宿・渋谷・池袋といった山手線沿線が繁殖地として機能し、千葉県の嶺岡などが供給地となりました。
岩手県においても、明治6年に盛岡で2件の搾乳業が始まった記録があり、そのうちの1件は旧盛岡藩士によるものでした。明治9年には県営の外山牧場が設立され、乳牛の繁殖が本格化します。岩泉から盛岡へと牛を送り出すネットワークが形成され、特に小泉家がその中心的役割を果たしました。
さらに、岩泉と盛岡を結ぶ「表街道」は、かつて塩の道としても知られ、牛の輸送にも利用されていたと考えられています。険しい峠を越えるために牛が使われ、街道沿いには牛のいる風景が広がっていたと推察されます。
講演では、Googleストリートビューを用いた現地の風景分析なども紹介され、酪農が地域景観に与えた影響が具体的に示されました。



講演3:農業遺産『重要文化財小岩井農場施設』
講師:辰巳 俊之 氏(公益財団法人小岩井農場財団代表理事 兼 小岩井農牧株式会社代表取締役社長)
辰巳氏は、小岩井農場の創業理念と施設群の歴史的価値について語られました。1891年創業の小岩井農場は、21棟の重要文化財を「リビングヘリテージ」として活用し続けており、これらの施設は明治〜昭和初期に建設された牛舎や倉庫などで、当時の最先端技術を反映しています。
職人技が光る建築様式が特徴であり、創業者の理念「美しい農場、従業員の幸せ」が現在も経営の根幹にあることが強調されました。
また、農地解放を免れた理由として、雇用型経営を採用していたことが挙げられ、施設の保存と活用が、地域の誇りと経済的価値の両立を可能にしていることが示されました。
小岩井農場の概要
- 創業:1891年(明治24年)、創業134年を迎える。
- 面積:約3,000ha(山手線内側の約半分に相当)。
- 主な事業:酪農事業と山林事業。
- 酪農:搾乳牛・肉用牛・育成牛合わせて約2,700頭。年間生乳生産量は約9,000トン。
- 山林:約1,950haの針葉樹林を管理し、持続的な伐採を実施。
- 飼料生産:牧草、トウモロコシ、小麦などを栽培。
重要文化財としての施設群
- 小岩井農場には21棟の重要文化財が現存。
- 明治〜昭和初期に建設された牛舎や倉庫などが、当時の最先端技術を反映。
- 特徴的な建築様式:
- キングポストトラス構造(柱1本で屋根を支える構造)。
- 赤松の板張りやドイツ式の特殊な張り方。
- 電気を使わない冷蔵庫など、手仕事による精緻な建築技術。
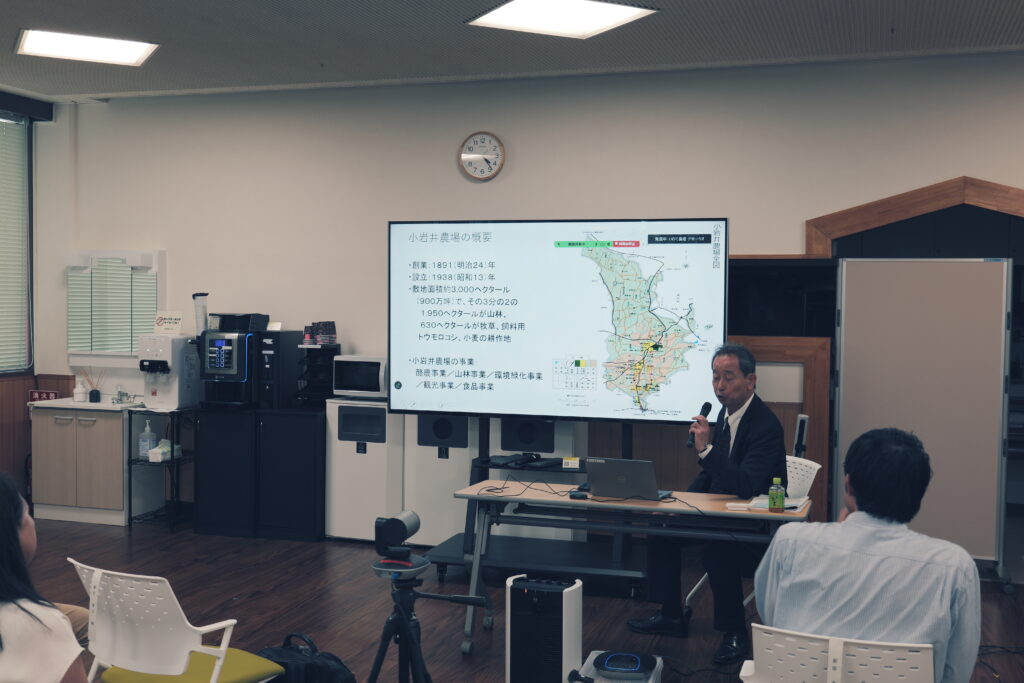


総合討論 畜産の多面的機能を見える化する
モデレーターの澤井先生進行のもと、登壇者とプロジェクト関係者による意見交換が行われました。


主な論点と意見
前田氏
- 見える化とは価値の顕在化であり、埋もれていた価値を発見・解釈し、物語化・ブランド化するプロセス。
- 景観には「自然景観」「歴史的景観」「農業景観」があり、農業景観は人々が生態環境と関わりながら形成してきた歴史の証。
- 見える化は「マーケットイン」ではなく「プロダクトイン」の発想で、地域の価値を社会のニーズに合わせて経済化することが重要。
金谷氏
- 見える化は「当たり前になっているものを歴史的に明らかにすること」。
- 岩泉だけでなく、盛岡・東京・横浜などとのネットワーク的なつながりの中で畜産の価値を再発見する必要がある。
- 歴史的な調査・研究を通じて、地域独自の景観や文化を価値として認識させることが見える化につながる。
辰巳氏
- 小岩井農場の見える化は「創業者の理念(美しい農場、従業員の幸せ)」に基づくもので、結果的にブランド価値を生んだ。
- マーケティングは得意ではないが、理念を守り続ける姿勢が見える化の成功につながっている。
- 「考え方 × 能力 × 熱量」という稲盛和夫氏の言葉を引用し、考え方の重要性を強調。
杉田先生(岩手大学COI-NEXT 課題4リーダー)
- 見える化の手法として「テリトーリオ・マップ」の活用を提案。
- 地元の若者と高齢者が協働して歴史を掘り起こすプロセスが、地域への愛着と理解を深める。
- 地図のような共有可能な形で価値を伝えることが、地域づくりにおける見える化の鍵。
まとめ
本セミナーは、畜産の持つ非市場的価値を地域社会の持続可能性と結びつけるための貴重な議論の場となりました。歴史・景観・理念・地域づくりといった多角的な視点から、畜産の未来を考えるヒントが数多く提示されました。
今後の「いわて畜産テリトーリオ」プロジェクトの展開においても、今回の議論が大きな指針となることが期待されます。

